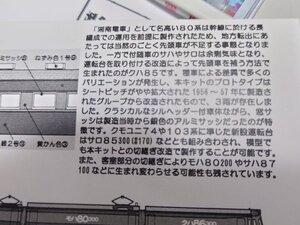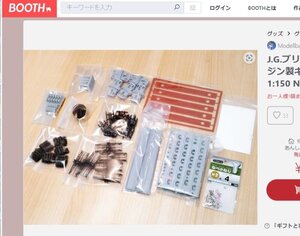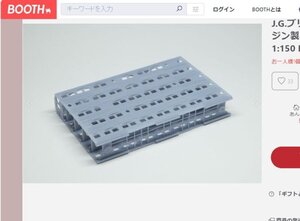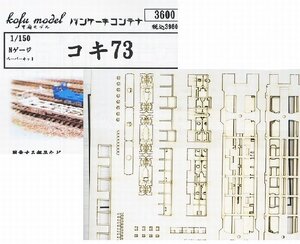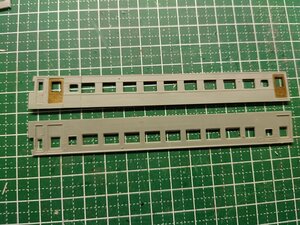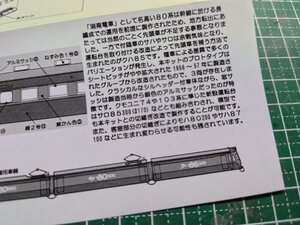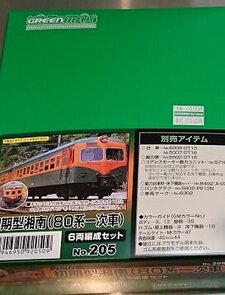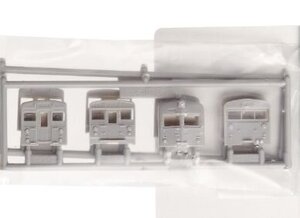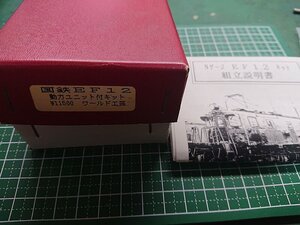KATOのニセコとC62北海道の久々の再生産で
今回からスロ62とスユ13のベンチレーターも別体化と言うことで
折角だから同時発売のアッシーパーツで旧製品もグレードアップ。
それぞれ2両分でスロは2310円、スユ(オユ)は1650円と
まあ安くはないがこのためだけに買い換えるのもアレなので
KATOのスロ62と10系客車は色々リファインされているものの
元は20世紀の発売製品なので旧43系ほどではないが
多少屋根ははずしにくいので慎重に
ところで久しぶりにバー銀座渋谷に行った。
コロナで銀座の方はやめてしまったが
渋谷だけはずっと健在。
今回は昭和13-14年富士と昭和19年富士を持っていって走らせた。